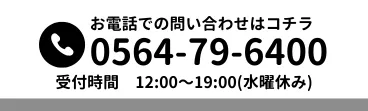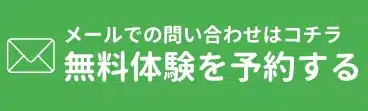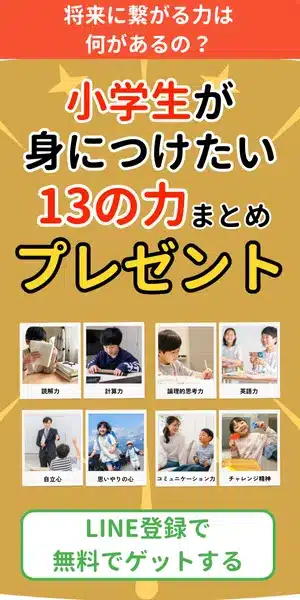「プログラミングって、うちの子にはまだ早いんじゃ…」
「中学校で必修化って聞くけど、ついていけるか心配…」
そんな不安や悩みを抱えていらっしゃる保護者の方、多いのではないでしょうか。
でも、大丈夫です。
この記事では、中学校で必修化されたプログラミング教育について、分かりやすく解説していきます。
「プログラミングって、実は身近なものだったんだ!」「うちの子にも、楽しく学ばせてあげたい!」
最後までお読みいただくことで、きっとプログラミング教育に対する見方が変わり、お子さんの未来を応援するヒントが見つかるはずです。
プログラミング教育は中学校で必修!内容や効果・家庭でのサポート方法を徹底解説【保護者必見】
「中学校でプログラミングが必修になったけど、具体的にどんなことを学ぶんだろう?」「家でできるサポートがあれば知りたい!」
そんな保護者の方々の疑問を解決するために、まずは中学校プログラミング教育の全体像を、一緒に確認していきましょう。
- 中学校プログラミング教育の現状と文部科学省の指導要領
- 中学校プログラミング教育で扱う内容は?
- 中学校プログラミング教育で使う教材は?おすすめツールも紹介
- 中学校のプログラミング教育はどう評価される?評価基準とポイント
- 中学校プログラミング教育はいつから?【私立と公立の違いも解説】
中学校プログラミング教育の現状と文部科学省の指導要領
2021年度から、中学校の「技術・家庭科(技術分野)」で、プログラミング教育が必修になりました。
参考:第3章 プログラミング教育の推進|文部科学省
これは、これからの情報化社会で活躍できる人材を育てるため、とても大切な取り組みなんです。
文部科学省が示す指導要領に基づいて、全国の中学校で、子供たちの情報活用能力を育むための授業が始まっています。
なぜ必修化されたの?
今の時代、私たちの身の回りには、スマートフォンやパソコン、インターネットなど、デジタル技術があふれていますよね。
これからの社会では、こうしたデジタル技術を使いこなし、情報を適切に選び、活用し、新しい価値を生み出す力が、ますます重要になってきます。
プログラミング教育は、この「情報活用能力」の土台となる、論理的に考える力や、課題を解決する力、創造力を育む上で、とても効果的なんです。
具体的に、どんなことが学べるの?
文部科学省は、学習指導要領で、中学校の「技術・家庭科(技術分野)」において、「計測・制御のプログラミング」や「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング」などを扱うことを示しています。
「なんだか難しそう…」と思われた方も、ご安心ください。
例えば、こんな話を聞きました。
「中学校の授業で、センサーを使った自動水やり装置を作ったそうです。最初は『難しそう…』と不安そうでしたが、試行錯誤しながら、最後は自分でプログラムを完成させることができた!って、目を輝かせて報告してくれました。家でも、もっと効率的に水やりする方法はないか、熱心に調べていますよ。」
このように、実社会と繋がりの深い学習を通して、子供たちは、自分たちの力で未来を切り拓く力を身につけているんですね。
文部科学省の指導要領に基づき、全国の中学校で、これからの情報社会で活躍するための力を育む、プログラミング教育がスタートしています。
「具体的にどんな内容を学ぶのか、もっと詳しく知りたい!」 そんな方のために、次の見出しで、授業内容や指導のポイントを解説しますね。
中学校プログラミング教育で扱う内容は?
中学校のプログラミング教育では、「プログラミング言語を使いこなすこと」がゴールではありません。
それを通じて、これからの社会で役立つ「プログラミング的思考」を身につけることが、一番の目的なんです。
「プログラミング的思考」って、何?
プログラミング的思考とは、簡単に言うと、「順序立てて、効率よく考える力」のこと。
何か課題にぶつかった時に、どうすれば解決できるかを順序立てて考え、実行し、改善していく。この力は、実はプログラミングだけでなく、どんな場面でも役立つ、将来必ず必要になる力なんです。
関連記事:プログラミング的思考とは?小学生低学年向け遊びで思考を伸ばす5つの方法
例えば、どんな風に学ぶの?
「朝、効率よく学校の準備をするにはどうしたらいいか」という日常的な問題を、プログラミングの考え方を使って解決してみる。
「まず顔を洗って、次に歯を磨いて、それから…」と、手順を細かく分解して、時間通りに、忘れ物をせずに準備するには、どういう順番で、何分で行動すれば良いのかを考えます。
これ、実はプログラミング的思考の第一歩なんですよ。
当教室であるPC堂パソコン教室でも、最初はローマ字を打つのも難しかった生徒さんが、授業を重ねる中で、「どうすればもっとスムーズにプログラムが書けるか」を、自分なりに工夫するようになりました。
試行錯誤する中で、自然と考え方が整理され、論理的に考える力が身についてきたんですね。
中学校のプログラミング教育では、プロのプログラマーを育てるのではなく、プログラミングを通して、これからの社会で必要とされる、論理的に考え、問題を解決する力、「プログラミング的思考」を育んでいるんです。
中学校プログラミング教育で使う教材は?おすすめツールも紹介
中学校のプログラミング教育では、難しいコードを書かなくても、パズル感覚で、楽しみながらプログラミングの基礎を学べる、そんな優れた教材がたくさん使われています。
なぜ、そんな教材を使うの?
いきなり難しいコードを入力するのではなく、最初は、カラフルなブロックを組み合わせたり、イラストを選んだりするだけで、簡単にプログラムが作れる教材から始めることで、プログラミングへの抵抗感をなくし、「楽しい!」「できた!」という成功体験を積み重ねることができるからです。
具体的に、どんな教材があるの?
例えば、世界中で大人気の「Scratch(スクラッチ)」は、ブロックを組み合わせるだけで、簡単にゲームやアニメーションを作ることができる、初心者向けのプログラミング学習ツールです。
また、小型のコンピューター「micro:bit(マイクロビット)」は、イギリス生まれの教育用教材で、センサーやLEDを使って、より現実世界とリンクした、実用的なプログラミングを体験することができます。
当教室の、Scratchを使った「Scratch(スクラッチ)講座」では、ゲーム作りに挑戦しています。
中学校のプログラミング教育では、生徒が楽しみながら、効果的に学習を進められるように、様々な工夫が凝らされた教材が活用されているんです。
「教材については分かったけど、プログラミングの成績ってどうやって評価されるの? テストの点数が悪かったらどうしよう…」
そんな不安を解消するために、次の見出しでは、中学校でのプログラミング教育の評価方法を詳しく解説します。
中学校のプログラミング教育はどう評価される?評価基準とポイント
中学校のプログラミング教育では、テストの点数だけが評価されるわけではありません。
プログラミングに取り組む過程で、どのように考え、どのように行動したか、そのプロセスも、しっかり評価されるんです。
なぜテストの点数だけじゃないの?
プログラミング教育で一番大切なのは、知識を覚えることではなく、それを使って、自分で考え、課題を解決する力を育むことです。
そのため、評価においても、結果だけでなく、そこに至るまでの過程、つまり、どのように考え、どのように取り組んだのかを、しっかり見ることが重要になります。
具体的には、どうやって評価するの?
具体的には、プログラミングの知識や技能を問うテストだけでなく、作品の制作過程で、どのように試行錯誤したのかを記録したノートや、発表会でのプレゼンテーションの内容なども、評価の対象となります。
結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスをしっかり評価してもらえるのは、子供たちにとっても、大きな励みになりますよね。
つまり、中学校のプログラミング教育では、知識・技能だけでなく、子供たちが主体的に考え、表現し、学ぶ姿勢を総合的に評価することで、一人ひとりの成長をしっかりと見守っているのです。
「プログラミング教育の評価方法、よく理解できました! それにしても、全ての公立中学校で、2021年度から必修になったんですよね?」 そんな疑問を解決するために、次の見出しで詳しく解説します!
中学校プログラミング教育はいつから?【私立と公立の違いも解説】
中学校のプログラミング教育は、2021年度から、全国の公立中学校で、一斉にスタートしました。
参考:学校情報化のこれまでの動きについて|文部科学省
ただし、私立中学校では、もっと前から、学校独自のカリキュラムで、よりハイレベルなプログラミング教育に取り組んでいるところも多いんですよ。
なぜ、私立と公立で違うの?
文部科学省は、2021年度から中学校の学習指導要領を改訂し、技術・家庭科(技術分野)においてプログラミング教育を必須の内容としました。
一方、私立中学校では、学校ごとに教育方針が異なるため、より自由に、より発展的な内容を、先んじてカリキュラムに組み込むことができるんです。
具体的に、どんな違いがあるの?
例えば、ある私立中学校では、数年前からAI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった、最先端のテクノロジーを学ぶ授業を取り入れています。
また、企業と連携して、実際に社会で使われている技術を学び、課題解決に挑戦するプロジェクトを行っている学校もあります。
一方、公立中学校でも、地域や学校の実態に応じて、特色あるプログラミング教育が行われるようになってきており、教育格差は是正されつつあります。
つまり、中学校のプログラミング教育は、2021年度から全国の公立中学校で始まり、私立中学校では、さらに先駆的でハイレベルな取り組みが行われているところもある、ということです。
「中学校入学前から、家庭でプログラミング学習の準備をしておきたいけど、何から始めればいいの?」 そう思われた方、ご安心ください。
次の見出しでは、家庭でできる学習準備について詳しく解説します。
【今からできる】中学校入学前に始めるプログラミング学習準備
「プログラミングって、なんだか難しそう…」と敬遠されていませんか?
実は、特別な塾に通わなくても、家庭学習でプログラミングの基礎を身につけることができるんです。
本章では、プログラミング学習を始める第一歩を踏み出すための方法をわかりやすく解説します。
- 【初心者OK】家庭で簡単にできるプログラミング学習環境の作り方
- 子供のやる気を引き出す!効果的なプログラミング学習サポート法
- 【無料あり】プログラミング学習におすすめの教材・アプリ・サイト10選
【初心者OK】家庭で簡単にできるプログラミング学習環境の作り方
実は、プログラミング学習を始めるのに、高価なパソコンや、難しいソフトは必要ありません。
まずは、ご家庭にあるパソコンや、インターネット環境を使って、お金をかけずに、気軽に始めてみましょう。
なぜ、お金をかけずに始められるの?
最近は、無料で利用できるプログラミング学習サイトや、スマホやタブレットで使えるアプリがたくさんあります。
これらのツールを使えば、難しい設定や準備をしなくても、遊び感覚で、すぐにプログラミングの基礎を学ぶことができるんです。
具体的に、どうすればいいの?
例えば、世界中で大人気の「Scratch(スクラッチ)」という学習サイトは、インターネットに繋がるパソコンがあれば、誰でも無料で利用できます。
カラフルなブロックを組み合わせるだけで、ゲームやアニメーションを簡単に作ることができるので、プログラミングが初めてのお子さんでも、夢中になって取り組めますよ。
このように、ご家庭にあるパソコンとインターネット環境、そして無料の学習ツールがあれば、今すぐにでもプログラミング学習を始めることができるんです。
それでも今のパソコンが古くてどんなパソコンを買ったら良いのか分からないから、安くて買い替えたい親御さんには、こちらがおすすめです。
|
|
「家庭学習でもプログラミングって学べるんですね!
でも、どうやって子供のやる気を引き出したらいいのかしら…?」
そんな悩みを解決するために、次の見出しでは、効果的な学習サポート法を伝授します。
子供のやる気を引き出す!効果的なプログラミング学習サポート法
子供のプログラミング学習をサポートする上で一番大切なのは、「やらされている感」をなくすこと。
子供自身が「楽しい!」「もっとやりたい!」と思えるような、そんな環境を作ってあげることが、何よりも重要です。
なぜ「やらされている感」をなくすことが大切なの?
子供は、自分が興味を持ったこと、楽しいと感じることには、驚くほどの集中力を発揮し、どんどん吸収していきます。
やらされる学習ではなく、自ら進んで学ぶ姿勢を育むことが、プログラミング学習を継続し、効果を高める、一番の近道なのです。
具体的に、どんなサポートをすればいいの?
例えば、子供が好きなゲームやキャラクターを題材にプログラミング学習を取り入れてみましょう。
「このキャラクターを、自分の思い通りに動かしてみたい!」という気持ちが、学習の原動力になります。
また、子供が作った作品を「すごいね!」「よくできたね!」とたくさん褒めて、認めてあげることも大切です。
当教室では、生徒が作った作品の発表会を開催したりしています。
子供の「好き!」という気持ちを大切にし、楽しみながら学べる環境を整えることで、プログラミング学習の効果を最大限に引き出すことができるのです。
「子供が夢中になれる教材があれば、もっと学習がはかどりそう! おすすめの教材を知りたいです!」
そんな方のために、次の見出しでは、私が自信を持っておすすめできる、学習教材やアプリをご紹介します。
【無料あり】プログラミング学習におすすめの教材・アプリ・サイト5選
子供向けのプログラミング学習教材やアプリ、サイトは本当にたくさんあります。
その中から、お子さんの年齢やレベル、興味に合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、プログラミング教育の現場に立ち、多くのお子さんを指導してきた私が、自信を持っておすすめできる選りすぐりの10選をご紹介します。
なぜ、子供に合った教材を選ぶことが大切なの?
教材選びは、プログラミング学習の成功を左右すると言っても過言ではありません。
お子さんに最適な教材やアプリ、サイトを見つけることができれば、学習の効率がぐんとアップし、モチベーションも自然と高まるからです。
具体的に、どんな教材があるの?
世の中には、本当にたくさんのプログラミング学習教材、アプリ、サイトがあります。
詳しくは、「【最新版】小学生向けプログラミング無料学習サイト・アプリ10選」で紹介しておりますため、ご覧ください。
お子さんの個性やレベルに合わせて、ぴったりの教材を一緒に見つけましょう。
「プログラミング学習のメリットを、もっと詳しく知りたい!」そんな方のために、次の見出しで詳しく説明します。
プログラミング教育が子供の将来に与えるメリットとは?【中学校で身につく力】
「プログラミングを学ぶと、どんないいことがあるの?」「将来、どんな仕事に役立つの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本章では、プログラミング教育がお子さんの将来に与える、様々なメリットについて解説します。
- 論理的思考力・問題解決能力が向上!プログラミングで社会を生き抜く力
- 中学校のプログラミング教育は進学・就職にどう影響する?
- テクノロジーの進歩に対応できる人材へ!プログラミングで広がる可能性
論理的思考力・問題解決能力が向上!プログラミングで社会を生き抜く力
プログラミング教育は、お子さんの論理的に考える力や、課題を解決する力を、ぐんぐん伸ばします。
これらの力は、これからの予測不可能な社会を生き抜くために、必ず必要となる、大切な力なんです。
なぜ、論理的思考力や問題解決能力が身につくの?
プログラミングでは、コンピューターに正しく命令を伝えるために、物事を順序立てて、筋道を通して考える必要があります。
また、思い通りに動かない時には、原因を探して、修正し、試行錯誤を繰り返しながら、課題を解決していきます。
このプロセスを何度も繰り返すことで、自然と論理的に考える力や、課題を解決する力が身についていくんです。
例えば、どんな場面で役立つの?
例えば、学校の宿題で分からない問題が出てきた時、「どこが分からないのか」「どうすれば解決できるのか」を順序立てて考えることができるようになります。
また、友達と意見が衝突した時にも、感情的にならずに、論理的に話し合って、解決策を見出すことができるようになります。
プログラミングで身につけた力が、日常生活の様々な場面で役立ちます。
「論理的思考力や問題解決能力って、生きていく上でとても大切な力なんですね。
他には、どんなメリットがあるの?」
そんな方のために、次の見出しでは、進学や就職への影響について解説します。
中学校のプログラミング教育は進学・就職にどう影響する?
プログラミング教育で身につけた力は、将来の進学や就職で、お子さんの大きな強みになります。
なぜ、進学や就職に有利なの?
近年、大学入試でプログラミングが試験科目に加わったり、AO入試や推薦入試でプログラミングの経験が評価されたりするケースが増えています。
また、就職においても、IT業界はもちろん、あらゆる業界で、プログラミング的思考や、デジタル技術を活用できる人材が求められています。
つまり、プログラミングを学ぶことは、お子さんの将来の選択肢を大きく広げることに繋がるんです。
具体的に、どんな可能性があるの?
例えば、将来、AI(人工知能)やロボット関連の仕事に就きたいと考えているお子さんにとって、プログラミングは必須のスキルです。
また、マーケティングやデータ分析など、一見プログラミングとは関係なさそうな仕事でも、プログラミングの知識があれば、業務を効率化したり、新しいサービスを生み出したり、活躍の場が大きく広がります。
「プログラミングを学ぶと、将来の可能性が広がるんですね!
でも、技術の進歩が早いから、今学んでも将来は変わってしまうかも…」
そんな不安をお持ちの方、ご安心ください。
次の見出しでは、その疑問にお答えします。
テクノロジーの進歩に対応できる人材へ!プログラミングで広がる可能性
プログラミング教育で身につくのは、単なるプログラミングの技術だけではありません。
新しい技術を学び、使いこなす力、つまり、テクノロジーの進歩に対応できる力そのものが身につくんです。
なぜ、テクノロジーの進歩に対応できるの?
プログラミングを学ぶ過程では、常に新しい情報に触れ、それを理解し、応用していくことが求められます。
この経験を繰り返すことで、未知の技術や、新しいツールに対しても、臆することなく、自ら学び、使いこなす力が養われていくんです。
将来、どんな仕事に就けるの?
今、世の中には、子供たちが大人になる頃には、今存在しない仕事がたくさん生まれていると言われています。
どんな仕事が生まれるのか、正確に予測することは難しいですが、一つ確かなことは、テクノロジーの進歩に対応できる人材は、どんな時代、どんな仕事においても必要とされる、ということです。
プログラミング教育は、お子さんが将来、どんな道に進んだとしても、必ずその土台となる、一生モノの財産になるはずです。
「プログラミング教育の必要性は分かったけど、なぜ中学校で必修化されたの?
もっと早くから始めるべきでは?」
そんな疑問を解決するために、次の見出しでは、プログラミング教育必修化の背景と、保護者の役割について解説します。
なぜ中学校でプログラミング教育が必修化?その必要性と保護者の役割
「そもそも、なぜ中学校でプログラミング教育が必修化されたの?」「私たち保護者には、何ができるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本章では、プログラミング教育必修化の背景にある、社会の変化と、これからの時代に求められる力について解説します。
そして、お子さんの学びをサポートする上で、保護者の方々にできること、その大切な役割について、一緒に考えていきましょう。
- プログラミング的思考とは?情報社会で活躍するための必須スキルを解説
- 中学校プログラミング教育の目的と家庭でできる効果的なサポート方法
- 子供の成長をサポート!プログラミング教育における保護者の役割と心得
プログラミング的思考とは?情報社会で活躍するための必須スキルを解説
「プログラミング的思考」は、これからの情報社会を生き抜くために、全ての人に必要なスキルです。
中学校でプログラミング教育が必修化された背景には、この「プログラミング的思考」を、全ての子供たちに身につけてほしい、という国の強い想いがあるんです。
なぜ「プログラミング的思考」が必要なの?
現代社会では、スマートフォンやインターネットを通じて、誰もが簡単に情報にアクセスできるようになりました。
しかし、その反面、膨大な情報の中から、本当に必要な情報を見極め、正しく活用する力が、ますます重要になっています。
プログラミング的思考は、情報を整理し、論理的に考え、課題を解決するための、強力な武器となるんです。
例えば、どんな場面で役立つの?
例えば、インターネットで買い物をするとき、たくさんの商品情報の中から、自分に合った商品を、効率よく見つけることができます。
また、旅行の計画を立てるときにも、目的地までのルートや、宿泊先、観光スポットなどを、順序立てて、効率よく調べることができます。
つまり、プログラミング的思考は、日常生活のあらゆる場面で役立つ、汎用性の高いスキルなんです。
関連記事:
プログラミングが使われているもの大百科!家電の秘密や身近なシステムを親子で学ぶ
日常生活で活用されるプログラミング例一覧!小学生向けに身近な具体例で紹介
「プログラミング的思考って、大人にとっても必要なスキルなんですね。
中学校のプログラミング教育の目的を、もっと詳しく知りたいです!」
そんな方のために、次の見出しで、さらに深掘りして解説します。
中学校プログラミング教育の目的と家庭でできる効果的なサポート方法
中学校プログラミング教育の目的は、プロのプログラマーを育てることではありません。
プログラミング学習を通して、論理的に考え、課題を解決し、新しい価値を創造する力を育むこと、それが真の目的なんです。
そして、その学びを支える上で、保護者の方々のサポートは、とても大きな力になります。
なぜ、プログラマーを育てるのが目的じゃないの?
「プログラミング」と聞くと、どうしても、専門的な仕事のイメージが強いですよね。
しかし、中学校のプログラミング教育は、将来、全員がプログラマーになることを目指しているのではありません。
どんな職業に就くとしても、どんな時代を生きるとしても、必ず必要となる、「考える力」を育むことが、一番の目的なんです。
家庭では、どんなサポートができるの?
「プログラミングなんて、教えられない…」と、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、大丈夫です。
専門的な知識がなくても、保護者の方々にできるサポートは、たくさんあります。
例えば、
- お子さんが作った作品を、一緒に見て、たくさん褒めてあげる
- 「どうやって作ったの?」「次はどんなものを作りたい?」など、積極的に質問して、会話を広げる
- 一緒にプログラミング学習サイトやアプリを体験してみる
- 「この機能、便利だね!」「どういう仕組みなんだろう?」など、日常生活の中で、プログラミング的な視点を取り入れてみる
大切なのは、お子さんの「好き!」「楽しい!」という気持ちを、温かく見守り、応援することです。
「家庭でのサポートが、そんなに大切なんですね。でも、具体的にどんなことを心がければいいのかしら…?」
そんな疑問を解決するために、次の見出しでは、保護者の役割と心得について、詳しく解説します。
子供の成長をサポート!プログラミング教育における保護者の役割と心得
プログラミング教育において、保護者の皆様は、子供たちの「伴走者」です。
子供たちの「好き」を尊重し、成長を温かく見守る。それが何より大切です。
具体的にはどんなことを意識すればいいの?
- 子供の「好き」を尊重する: 子供が興味を持ったことを、否定せずに、一緒に楽しむ。たとえそれが、一見「無駄」と思えるようなことでも、子供の「好き」という気持ちは、大きな可能性を秘めています。
- プロセスを大切にする: 結果だけでなく、そこに至るまでの過程、子供がどのように考え、どのように取り組んだのかを、しっかり見てあげる。たとえ失敗したとしても、そこから学び、次に繋げることができれば、それは大きな成長です。
- 「教える」のではなく「一緒に学ぶ」: プログラミングは、大人にとっても、新しい学びの連続です。子供と一緒に試行錯誤することで、親子の絆も深まり、子供の成長をより身近に感じることができるはずです。
- 成長を長い目で見守る: プログラミングに限らず、子供の成長には個人差があります。周りの子供と比べたり、焦ったりせず、子供自身のペースを大切にしてあげましょう。
当教室では、保護者の皆様と連携しながら、お子さん一人ひとりの成長を、全力でサポートしています。
「プログラミング教育について、もっと詳しく知りたい!」「うちの子に合う学習方法が知りたい!」
そんな方は、ぜひ一度、PC堂パソコン教室に、ご相談に来てくださいね。
プログラミング無料体験会(1回50分/随時開催※保護者同伴)
お子さんの可能性を広げる、最適な学びを、一緒に見つけましょう!
「プログラミング教育について、よく分かりました。でも、実際に中学校の授業でどんなことを質問されるんだろう…?」そんな疑問を解決するために、次の見出しで、よくある質問をまとめてみました。
中学校のプログラミング教育でよくある質問
ここでは、中学校のプログラミング教育について、保護者の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめています。
「こんなこと聞いてもいいのかな…」と遠慮せず、どんな些細なことでも、参考にしてみてくださいね。
- 中学校のプログラミング教育の内容は何ですか?
- プログラミングは中学で必修ですか?
- 中学校で学ぶプログラミング言語は?
- プログラミング教育の欠点は何ですか?
Q:中学校のプログラミング教育の内容は何ですか?
A:中学校のプログラミング教育では、プログラミング言語の習得だけを目的にするのではなく、物事を順序立てて効率よく問題を解決できる力「プログラミング的思考」を養う事に重点が置かれています。
そのため、実際に授業では、試行錯誤を繰り返して、生徒自身が論理的に考える練習が行われています。
関連記事:プログラミング的思考とは?小学生低学年向け遊びで思考を伸ばす5つの方法
Q:プログラミングは中学で必修ですか?
A:はい、2021年度より中学校でプログラミング教育が必修化されました。
参考:第3章 プログラミング教育の推進|文部科学省
今は、デジタル技術の活用が当たり前の時代です。
デジタル技術を使いこなし、情報を適切に取捨選択して活用し、新しい価値を生み出す事はとても重要です。
そのため、プログラミング教育は、「情報活用能力」の土台となる、論理的に考える力や、課題を解決する力、創造力を育む上で、とても効果的と考えられており、大変重要な役割を果たすのです。
Q:中学校で学ぶプログラミング言語は?
A:中学校で学ぶプログラミング言語は、主に「Scratch」や「JavaScript」など、学校によって異なります。
「Scratch」は、カラフルなブロックを組み合わせるだけで、簡単にゲームやアニメーションを作ることができる、初心者向けのプログラミング学習ツールです。
関連記事:Scratch(スクラッチ)講座
「JavaScript」は、中学校で学ぶ数学や英語と同じような「言語」の一つです。
「JavaScript」を学ぶ事で、Webサービスをつくる事ができます。
その他、小型のコンピューター「micro:bit」を用いて、センサーやLEDを使った、より実用的なプログラミングを体験する学校もあります。
関連記事:【最新版】小学生向けプログラミング無料学習サイト・アプリ10選
Q:プログラミング教育の欠点は何ですか?
A:プログラミング教育の欠点は、教員のITスキルや知識に差がある事です。
ですが、プログラミング教育の導入から数年経ち、文部科学省が教員向けの研修に力を入れている事もあり、徐々に差が無くなりつつあります。
また、プログラミング教育は、あくまでもプログラミング的思考を学ぶ事が目的です。
プログラミング言語を使いこなす事ではない事を理解しておきましょう。
まとめ:中学校プログラミング教育は子供の未来への投資!今からできることを始めよう
中学校で必修化されたプログラミング教育は、お子さんの将来を豊かにする、かけがえのない「未来への投資」です。
「プログラミングは難しい」と敬遠せず、まずは、できることから少しずつ、始めてみませんか?
当教室では、無料体験授業や、個別相談会を随時実施しています。
プログラミング無料体験会(1回50分/随時開催※保護者同伴)
「プログラミング教育について、もっと詳しく知りたい!」「うちの子に合う学習方法が知りたい!」
そんな方は、ぜひ一度、当教室までお気軽にご相談ください。
お子さんの可能性を広げる、最適な学びを、一緒に見つけましょう。
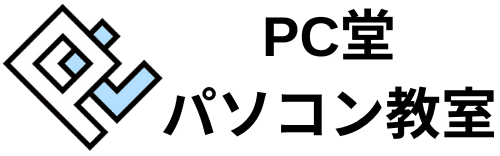

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4291339e.26fcd380.4291339f.d605e676/?me_id=1394396&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falot-tokaku%2Fcabinet%2F08073522%2F10272635%2F10272637%2Fshift-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)